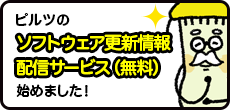2017年5月24日更新美女と野獣は人間の本質
実写版映画「美女と野獣」を観てきました。アニメ版は1991年公開ですので、今40代・50代の方は、映画館デートでご覧になった方も多いのではないでしょうか? 今回の実写版は確かに「アニメ版のリメイク」ではあるのですが、そう思っていた自分の予想は大きく裏切られることになりました。結論は、前作を遥かに超越した歴史的傑作です。

今さらご案内するまでもない、皆さんご存知のストーリーは変わりなく、「少し変わり者の美女ベルが、魔法で醜い野獣に変えられてしまった王子と恋に落ちる」という大筋はそのままですので、ここは子供でも楽しめる展開です。本作が凄いのは、元々アニメ版でも描かれれていた“重要な要素”をより深く掘り下げることで、大人の心を強く揺さぶる普遍的なメッセージが散りばめられているところです。
たとえば「外見」。「人は見かけによらぬもの」と言いますが、実際の人物評価は見かけに大きく依存してしまうのが常です。物語の冒頭、虚栄にまみれた王子は、毎晩のように城に美女とぜいたく品を集め、パーティを催して悦に入っていました。華やかですが中身はありません。若くして母親を亡くし、厳格な父に育てられた王子は、愛を知らないため、本当に心を満たすものが他にある、ということを知りません。愛は知らない一方、自分がハンサムであるということは知っているため、見かけが100%だと思い込んでいます。
ある嵐の夜、雨宿りを求めて城を訪れた老女が差し出した一輪のバラ。王子は年老いた老女の見かけだけで「醜い」と判断し、追い払おうとします。ご存知の通り、この老女は魔女。見かけで判断した王子の眼前で、老女は美しい魔女へと変貌します。見かけでしか判断できない王子、今度は手のひら返しで謝り、許しを請いますが、時すでに遅し。魔女がかけた魔法により、王子は醜い野獣へと変えられ、白亜の城は暗い悪魔の巣窟に、そして召使い達はランプや時計、ポットといった日用品に変えられてしまいます。
アニメ版ではステンドグラスのみ、しかも数分しか描かれなかった冒頭のシーンが、実写版ではより長く詳細な表現とすることで、「見かけで判断することの愚かさ・怖さ」を強烈に印象付けています。しかも、本作では城に住む人々のことを、城外の人々は「忘れてしまっている」という新たな設定が加えられました。誰からもかえりみられることのない、孤独な城。外見がすべてだと思い込んでいた者たちに、裁定者たる魔女はみじめな外見だけでなく社会との断絶という罰も与えました。苛烈な魔法を解くには、傲慢で愛を知らぬ王子が誰かを愛し、かつその相手からも愛されなくてはなりません。愛とは自分よりも他人のことを大切に思うこと。「誰も一人では生きられないのだから、愛することを学びなさい、それができないなら獣や物と同じですよ」ということですが、文字にすると強烈過ぎるメッセージです。
一方、ベルが暮らす小さな村の住人達も実は同じです。ベルは特別なことをしているつもりはないのですが、「女のくせに本が好き」「変な発明をする父親と変な娘」というレッテルを貼られ、浮いた存在になっています。村人たちは変化を嫌い、極めて強い同調圧力を持っているため、たとえ違和感があってもそこから抜け出したら最後、自分も浮いた存在になってしまいます。浮いている者は他にもいて、未亡人で物乞いをしているアガットも同じですが、ベルはアガットにもパンを分け与えるなど、属性や見かけで分け隔てることはしません。彼女は正しいことをしているだけですが、村の中では孤独で、生きづらさを感じています。なお、見かけに囚われてはいけない、という伏線は、すでに冒頭からあちこちに張り巡らされています。
そのベルに何度も求婚する粗暴な自称伊達男ガストンは、「見かけ100%」の典型です。ベルが変わり者だと知っていても、見かけが美しいので他の要素は無視。美しい嫁に美しい子供を産ませることで、カッコいい俺はよりカッコよくなる、という計算だけ。ベルを愛してなどおらず、それどころか自分のことも愛してはいないのに、カッコいいから愛されて当然と思い込んでいる。
結局、王子もガストンも村人もみな同じで、人をうわべだけで判断し、自分と違うものは「変だ」と蔑んでかえりみない。自分が逆にそうされるのが怖くて不安なため、「変」な他人を蔑んで不安を和らげようとしているのです。特に村人たちの「不安」は、物語後半で爆発することはご存じのとおりです。
アニメ版より掘り下げているところは、他にもあります。たとえば、ワガママで見てくれ命だった王子様が野獣に変えられるのは理屈としてわかるのですが、召使い達までモノに変えられてしまうのは、連帯責任としてもやりすぎじゃないの?と思ったのは、私だけではないでしょう。しかも、アニメ版と違って今回の召使いたちは「王子が愛に目覚め、かつ愛されなければ野獣のままとなり、召使いたちは単なるモノになってしまう」こと。つまり、最後の花びらが散るタイムリミットまでに「愛し、愛される」というミッションが果たされない場合、召使いたちは永遠に人間の姿に戻れないどころか、魂さえ失って単なるモノになってしまうのです。アニメ版よりはるかに過酷な運命を背負わされていると思いませんか?
これについて、ベルが「なぜあなた達まで魔法にかけられてしまったの?」と問うシーンがあるのですが、この答が印象的です。
「ご主人様が母君を病気で失い、厳格な父君の躾けのせいであんなふうに歪んでしまうのを、我々は止めずに黙って見ていたから」
つまり、王子は悪いけれど、周りの部下たちも悪い。魔法はその罰だというのです。物語では、ベルが城を訪ねた時点で魔女の呪いをかけられてから10年経っている設定です。その間、野獣になった王子もさることながら、モノにされてしまった召使いたちも想像を絶する葛藤があったことでしょう。そのきっかけを作った王子に恨みを持ったとしても不思議はありません。
ところが、ベルに「なぜ、ここから逃げないの?」と訊かれたポット夫人はこう答えます。
「ご主人様は見た目ほどひどい人ではないのですよ」
自分の運命が尽きるかもしれない瀬戸際でも、召使いたちは主人に対する希望を捨てていません。あるいは10年という長い共同幽閉生活を経て、ようやく主人の心の中にあるあたたかさに気付いたのかもしれません。そこには揺るぎない信頼関係が透けて見えます。
一方で、野獣はベルに「いつも楽しそうな召使いたちの輪に入れない」「自分が行くと、彼らの笑顔は消えてしまう」と、孤独感を打ち明けます。召使いたちの振る舞いに理解を示しつつも、距離感に悩んでいるわけです。「あいつら、俺のいないところで言いたい放題だろう」といじけている上司が(私も含めて)ほとんどですから、部下にここまで配慮している野獣・・・なんと素晴らしい上司でしょう。王子の本当の気持ちがわかるからこそ、召使いたちも王子に対して粗野なふるまいを諌めたり、おめかしや入浴を手伝ったりできるわけです。(もちろん、自分が人間に戻りたいという打算も間違いなくありますが。)
野獣が打ち明けた孤独感は、ベルも感じていました。本の虫で進取の精神に富むベルは、女は本など読まない小さな村では変人扱い。完全に浮いた存在で、誰ひとりまともに向き合ってくれません。「シェイクスピアが好き」というベルに対して、野獣は「君なら別に驚かないね」と理解を示した上で、膨大な蔵書がある城の書斎にベルを案内し、どれでも好きなだけ読んでいいと告げます。何千冊という本を前に大喜びで「これ、あなたは全部読んだの?」と問うベルに、「勘弁してよ、ギリシャ語はわからない」と、見かけに似合わないジョークで返します。王子はシェイクスピアの一節をそらんじるなど知的な一面をのぞかせますが、ガストンと違ってそれをひけらかしたりせず、「教育にカネがかかっているだけ」と冷静に自分を捉えています。野獣が「女性だから本は読まない」という当時当たり前の偏見に縛られていないことに驚くベル。ベル自身も、野獣の見てくれにひるまず王子の素顔をまっすぐ見つめます。読書という共通の趣味と孤独感を共有するこのくだりも、アニメ版ではただ書斎に案内するだけでしたが、実写版では二人の距離が大きく縮まる大切なシーンに仕上がっています。
物語の終盤、ベルが魔法の道具を使って見せた野獣の姿に恐怖を感じた村人は、野獣を倒すため暴動を起こします。野獣は村人に対して、何の危害も加えてはいませんが、「放っておくと危ない」という思い込みだけで野獣を排除しようとする暴挙を正当化するのも「見かけ100%」と不安のなせる業です。ベルの父親はある理由からパリを離れ、この田舎町に移り住みました。それは、ここが「小さな村」で「小さい」ということは安全だから、という理由でした。一方で、「小さな村」の人々はSmall-minded、つまり考え方も小さいと指摘します。視野が狭いから、自分の小さなコミュニティとその中での規範が全て。それ以外のものや新しいものは「リスク要因」であり、日々の平穏が全てのSmall-mindedな人たちには受け入れられません。その懸念は、野獣の(見かけだけの)不安に駆られたことによって冷静さを失い、邪悪な形で噴き出してしまいます。村の外には、大きな世界が広がっているのに、小さな視野でしかものごとを見ようとしない。彼らの本質はまさに「野獣」です。
あなたの心は、美女ですか?それとも野獣でしょうか?
城の暗がりで初めて野獣に対峙したとき、ベルは”Come into the light.”、「光のもとに出てきて=姿を見せて」と言います。誰もが「美女=美しい素顔」を心に秘めていても、日々の生活や忙しさを言い訳に粗暴な野獣となり、曇ったSmall-mindedな世界に引きこもってしまう。本当は、みな見た目にとらわれずに本質を見てほしいと思っているからこそ、そこに光を当てた本作は心を打つのでしょう。
私はすでに3回観たのですが、初回では最も輝きを放っていたのはベルの美しさでした。ところが、見る回を重ねるごとに、今度は野獣の繊細かつ豊かな表情に惹きこまれて、野獣の視点に共感するようになっていきました。野獣を演じたダン・スティーヴンスは、重さ20キロのボディスーツを着用し竹馬に乗って演じただけでなく、同じシーンを今度は顔だけ撮影するために二度演じたそうです。その後、デジタルペインティングで顔に野獣の毛を「植毛」する作業を1年かけて行うという、気の遠くなるようなプロセスを経て野獣は完成しました。見かけは野獣でも、喜怒哀楽を生き生きと描くことで、葛藤や愛憎を抱えた王子の細やかな内面とその変化に共感してほしい、という制作側の希望がそこにあらわれています。ベルとの出会いによって、自らの過ちに気付き自暴自棄の一歩手前で踏みとどまった野獣は、残る花びらが一枚になっても自分の運命から逃げずに立ち向かいます。野獣がガストンと戦う場面は、人間の姿をした野獣と、野獣の姿をした人間の対比になっているのですが、誰一人外見など気に留めないほどの緊迫感です。
美女と野獣がダンスを踊る歴史的シーンは今作でも大きなクライマックスですが、ベルと野獣がくるくると入れ替わるように、人生の節目節目で本当の姿を光のもとで輝かせられるといいですね。
深みを大きく増したストーリーを彩るのは、アニメ版から27年を経てなお全く色褪せない、名曲の数々と圧倒的な映像美。「本気」のディズニーが織りなすミュージカルの真骨頂に、ぜひ劇場で酔いしれてみてください。

記事一覧
- SNJメンバーと小室山リッジウォーク散策
- サンタクロースの季節
- 創立75周年ビデオ制作
- 嵐の中のLes Cordes生音ライブ
- 予約の多い美容院
- 土佐旅行記
- 身分証明書
- ウェルビーイングについて考えてみた
- デジタル時代の働き方
- 村上春樹ライブラリー
- SDGsについて考えてみた
- 雨の日も心が晴れる永井宏さんの本
- ジェンダー・ギャップについて考えてみた
- コロナ終息後の個人的行動計画
- コロナ禍に響くハンドベルの音色
- 秋の夜長にバルミューダスピーカーで聴くジョニ・ミッチェル
- テレワーク中の過ごし方
- 健康診断はお好きですか?
- フランス人は結婚しない?
- ラクして美味しいチリ
- 幸せになるには
- ひこうきぐも
- チャイナタウンへようこそ
- 備えあれば憂いなし ~災害に備えよう~
- ジャズピアノはじめました
- 健康・快適・そして若さにも? 欠かせないのは適度な湿度
- バカンス効果
- お客様との関係は恋愛に似ている?
- オーストラリア・フィリップ島の世界一小さなペンギン
- 誰でもできる涼しくなる呼吸法
- フルーツの魔法でフツーのワインがおしゃれなカクテル「サングリア」に変身
- 洋式競馬発祥の地と「天野喜孝展 天馬」
- もったいない「食品ロス」、どうすれば減らせる?
- 「50歳アニバーサリーライブ」体験レポート
- ヤッホーではない自転車事故の現状
- 懐かしのエスニックフード ~ 米国編・日本編
- 私流 英語の発音上達法
- 桜にまつわるエトセトラ
- ランチ後の睡魔撃退実証実験
- あなたの知らないアメリカ
- 腰痛持ちのあなたにお勧め~続けてみようYOGA
- プチ・タイムトリップはいかがですか? 小倉百人一首の世界
- リスクとハザードは違います「富士山噴火?するわけねーじゃんww」
- アラフィフのパワー全開、最強教員バンド
- モントリオールの地下鉄
- 疲れた時に効(聴)く音のビタミン剤、Pentatonix
- 恩師との再会
- 機械安全LOTOセミナー in 名古屋&大阪 お申し込み方法のご案内
- 恩師を偲ぶ
- Message from the Wine Shop Owner
- ワイン専門店オーナーからのメッセージ
- Wine Specialty Shop in Germany
- ドイツのワイン専門店
- 現代英国に舞い降りた吟遊詩人 エド・シーランの世界
- Why Europeans Get a Tattoo is Different from Japanese
- 欧州と日本
まったく違うタトゥー(入れ墨)事情
〜リアルインタビュー〜 - 夏の風物詩を一足先に味わえる夜
- 美女と野獣は人間の本質
- ドイツ・ハンブルクで見た 印象深かったことトップ3
- ダイエットと言い訳
- ワシントンから横浜へ里帰りした「シドモア桜」
- 「君の名は」だけではない!RADWIMPSの魅力
- あなたもわたしも「ラ・ラ・ランド」
- 初めての古澤節を聴いて・・・
- 「安心」と「安全」は違います
- 戦場カメラマンが贈る言葉
- 思い出厳選BOX(完成はいつだろうか?)
- リスクを取ってこそ、安全は生まれる
- 「道」は続く
- ゴジラは日本代表
- Rioが終わり・・・Tokyoへ
- バイトテロはリスクの本質を物語る
- 家猫状態のリフレッシュ休暇
- ドイツのおすすめビアカクテル