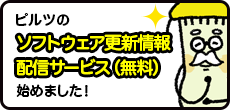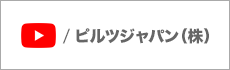2025年3月19日更新安全衛生推進者の役割について~そのⅠ~
岩手県大船渡市の大規模な山火事、長野県や山梨県でも山火事発生、アメリカロスアンゼルス近郊の山火事など気候変動による災害と言われものが多く発生しています。被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げたいと思います。自然には勝てませんがその「背後要因」に対する対策は人間の英知で解決していけるものもあると思います。今回は、労働災害の減災のための活動を推進する人たちにエールを送り、役割などについて一緒になって考えてみたいと思います。
1.安全活動は“誰のため・何のため・いつ使うため?”の活動か
(1) 腹落ちした活動
今までこのコラム欄で多くのことを伝えてきました。主にスタッフの人たちにエールを送りたいという心境で書いてきましたが、改めて私たちの活動が現場の人たちに歓迎されるためにはどうすれば良いか考えてみたいと思います。昨年とても良いことがありました。年初には、10数年ぶりに設備メーカで講演をしました。私の時代に現場へ落とし込んだ活動が社長・役員が何人も代わっても安全活動は継続されていました。また、年末には、九州の自動車会社でも講演を10数年ぶりに実施しましたがその時工場巡視をさせてもらいました。驚いたことは以前より遙かに素晴らしい活動になっていたことですが、そのベースになっている活動が私の時代にみんなと一緒に作り上げた活動でした。言葉もそのまま使われていました。なぜでしょうか?「経営者から作業者まで腹落ちしている」からだと思います。原因はいろいろありますが、最も大きいのは「現場目線」の活動をトコトン追求したからだと思っています。「命を守る活動」は普遍だからだと思います。
(2) 上目線の活動からの脱却が必要
現在も、多くの事業所で指導を続けさせてもらっています。課題のない会社はありませんが、「上から言われているから」やっている活動であったり、「法を盾にとった指導」であったり、「指示待ち人間が増えてしまっている」状況であったり、本来の「現場目線」がかけていることを相変わらず多く見かけます。時代背景もあって「管理者が板挟み」状態になっていることもあります。しかし、折角「命を守る活動」を任されたのならまず自らが「活動を腹落ち」させなければ相手に伝わりません。災害(怪我と・疾病)は、「職場の問題の代表特性」と考えています。「ルールを守らない」「危険予知能力が足りない」のではなく、「守りやすい、シンプルなルールとしていく」「足し算ばかりのルールづくりから引き算のルールづくりへ」とか、「専門技能研修を充実させて、危険予知力を高める」「人事制度を変えていこう」「機械安全の組織横断的統一」など組織的な問題へのアプローチをしていくことが社長から業務委託されている安全衛生の仕事ではないでしょうか。腹落ちするための切り口は多くあります。挑戦的な楽しい仕事だと思います。(それぞれの進め方は、今回は省きます)
(3) 形骸化した活動からの脱却
常に申し上げていることです。雇用形態の変化など労働環境も様変わりしていますが、4日以上の休業件数が相変わらず上昇傾向にあるのになぜ活動の中身を見直さないのでしょうか。以前からやっている活動だからと活動の真の目的を忘れ、形だけの活動であったり、活動が目的化していることなどに気付き、変えていく努力が必要です。それぞれの活動が「誰のため・何のため・いつ使うため」という点の腹落ち感がなさ過ぎるからだと思います。間違っていても良いので自分自身で腹落ちさせて下さい。間違っていたと思ったら変えれば良いことです。自分自身が腹落ちしていない活動が、他人の心を動かせるはずがありません。
2.安全衛生部署の役割とは?
(1) 半歩前一歩前の活動
「災害が起きてからなら誰でも言える」という言葉は、私が一年目の時、災害が発生した職場に行ったときに知人から言われました。「その通りだ」と思い、「未然防止」に大きく舵を切り、「重点災害未然防止活動」を推進し始めました。災害には、「背後要因」があると考え、「全ての領域にものが言える唯一の領域」、「死亡・重篤な災害だけは絶対出したくない」と言う執念に近い考え方がおぼろげながら浮かんだのがもう四半世紀以上前のことです。その活動を実践して10数年後に、法律で「リスクアセスメントの実施(重篤災害の未然防止活動が主目的)」や「機械の包括的な安全基準に関する指針(12100がベース)」が出されました。また、「非定常作業の洗い出しと改善活動(製造業の最大のターゲット)」に関するガイドラインなどが出されました。これらは、半歩前一歩前の精神で考え実践してきた活動が認められたと感じました。
(2) 活動の心・目的の伝承
1.で10数年後に元職場を訪ねた感想を述べましたが、活動だけを継続したのであれば、これほど定着はしなかったと思います。安全衛生推進者が「語り部」となって「なぜ活動ができたか」、「なぜルールができたか」などの“背景を教え伝えていく仕組みと努力”があったからだと思います。一言で言えば「管理者研修」が落としどころの一つだと思います。外部研修に委託しては、社内で実施してきた活動の歴史や背景が伝えられません。「人づくりにかける時間を惜しんでは将来が危うい」と思わないことが不思議です。私は、指導の中で必ず「教科書づくりと、講師づくり」を提案します。なかなか時間がかかりますが、やっていけば安全衛生推進者の仲間も増え、自信にもつながっていくはずです。役割としては、この仕事がもっとも大きいと思っています。
(3) 組織横断的活動の推進
安全衛生だけでは、減災活動の推進は難しいことは当然です。災害の背後要因には、組織共通の課題が見えてくるはずです。各職場単位では解決できない要因を安全衛生推進部署が取り上げ、プロジェクトなどの組織化をして進めていかねば解決しないと考えています。この活動を進めていくことには、相当の覚悟と仲間作りにかける努力が必要になります。しかし、これこそがやりがいだと思います。他の領域でこうしたことのできる組織はないと思います。ファイト!です。
※さらっと書きましたが、一つひとつの言葉が深いです。是非、仲間(同志)で議論して欲しいです。語り合うことが必要です。まだまだ切り口はありますので次回も触れたいと考えています。そして、皆さんの議論を元にもっと深掘りして語りあいたいですね。私の多くの失敗を皆さんにして欲しくないので、私の経験の全てをお伝えしたいと考えますが現場で実体をみつつ、対面で実施しないと伝わらないと思います。機会が作れると良いのですが‧‧‧。是非、意見・質問・コメントをいただけると嬉しいです。

記事一覧
- 安全巡視は人づくり
- 野菜づくりと人づくり
- 安全衛生推進者の役割について~そのⅡ~
- 安全衛生推進者の役割について~そのⅠ~
- ヒューマンエラーは原因でなく結果
- 日本の明日は大丈夫?
- “話す力・伝える力”と“言葉の意味”を考えてみる
- 安全活動は足し算?引き算?
- コミュニケーション力向上の心構え
- 最近の関心事から“雑感”
- 安全教育を充実させていく“肝”
- 先人の偉業と教訓そして実践
- サッカーワールドカップと俯瞰力
- 安全衛生法制定50周年と今後のあり方考察
- 水の大切さと恐ろしさ
- 冬季オリンピックと平和を考える
- コロナ禍の教訓を労働安全活動に活かす ~2021全国産業安全大会・講演要旨~
- モノの見方・考え方を一考する ~本:“どうせ死ぬから言わせてもらう”から~
- 正直に生きる・語ることの大切さ ~“生き様”を振り返る~
- 新型コロナ禍の更なる課題・再考 ~件数・パフォーマンスより内容重視の活動へ~
- 安全衛生方針の重要項目と展開ポイント ~絞り込みと運用マニュアルの活用~
- “新型コロナ禍”から考える教訓-2 ~行動の変化~
- 思い込みの怖さと正しい判断・行動 ~ “新型コロナ禍”から考える教訓~
- “野村克也元監督”の教え・あれこれ ~人を育て残す事の大切さ~
- “ラグビーロス”とその後~“ラグビーワールドカップの感想と実践の大切さ“~
- “人間性(心の持ち方)”について考える~ラグビーワールドカップと“故・平尾誠二氏”の生き方~
- より・安全で、安心な時代“令和”をつくろう~“平成”を考えつつ~
- 継続と深掘り・“不断”の努力の大切さ~“東日本大震災”から丸8年~
- チームワークとリーダーの役割
~“大坂なおみ”全豪オープン優勝~ - ポジティブシンキングの実践 ~“箱根駅伝”の教訓~
- ”腹落ちさせる指導”について考えてみよう ~その4(最終回) 「足:踏み込む」について~
- ”腹落ちさせる指導”について考えてみよう ~その3「口:問う」について~
- ”腹落ちさせる指導”について考えてみよう ~その2「目:観る」について~
- ”腹落ちさせる指導”について考えてみよう ~その1「耳:聴く」について~
- ”環境”の大切さと人の行動 ~“命を脅かす”気候変動~
- まず”減災” 目ざせ”ゼロ災” ~大阪北部地震の教訓~
- “危険なタックル問題”から人の育て方を考える
- 作業標準書・作業手順書の作り方と活用法 ~“守・破・離”の心~
- 薬傷災害から活かし方・つなぎ方を再考する ~事後の百策より事前の一策~
- 気づかい・個のレベルアップとチームワーク ~平昌オリンピックの感動からの教訓~
- 後継者・人の育成を考える ~人の成長をどのようしてサポートするのか~
- 気づき・気がかり粗末にするな 気づいたらすぐ行動に移せ!
- 安全活動と品質活動の“根っこ”は同じである ~安全活動から“本音の活動”を深掘りしよう~
- 機械安全基準の制定と進め方 その2 ~安全・品質・環境は企業活動の根幹である~
- 機械安全基準の制定と進め方 その1 ~激しい向かい風の中を”航行”~
- 「そうだ、古澤先生に聞いてみよう」コーナーへのご投稿について
- 実践的なリスクアセスメントの進め方
~隔離対策のポイント~ - 新コーナー【そうだ、古澤先生に聞いてみよう!】いよいよスタート!
- 実践的なリスクアセスメントの進め方
~「現場リスクアセスメント」の進め方~ - 実践的なリスクアセスメントの進め方 ~重篤な災害に的を絞った洗い出し~
- 安全衛生方針の作り方・活用の仕方
~もっとわかり易く~ - 1年間を振り返って ~現場目線からの提案と報告~
- 非定常作業に特化した活動‥その4 ~重要な柱「ソフト対策」の進め方~
- 非定常作業に特化した活動‥その3 ~真の要因に対するハード対策の推進~
- 非定常作業に特化した活動‥その2 ~洗い出しのキーワードとカイゼンの実践~
- 非定常作業に特化した活動 その1 ~定義付けと洗い出しのポイント~
- 管理者研修の実践 ~第75回全国産業安全衛生大会(in 仙台)講演骨子~
- “新しい安全”「Safety 2.0」と言う考え方
- 重篤災害に的を絞った活動の勧め
- 人を育てる安全巡視の進め方
- 「みる」と「みえる」の違い
- 安全活動はカイゼンの入口と捉えてみよう
- 腹落ちした活動とするには「具体化」と「共有化」
- 産業現場で起きている災害の現状と課題
- 古澤 登(ふるさわ のぼる)プロフィール